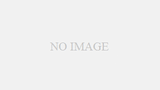こんにちは、からすこです。
さっそくトレーニングです。
与件文
A社は、地方都市X県の中心市街地と郊外に計3店舗の和食飲食店を展開する中小企業である。創業は昭和20年代後半。戦後の復興が進む中、初代社長が駅前商店街の一角に小料理屋を開いたのが始まりである。当初は、地元の漁港から仕入れた新鮮な魚を使った煮付けや刺身定食などを昼夜提供する、大衆向けの家庭的な料理店として親しまれていた。
二代目が事業を継承した昭和後期には、バブル期の接待需要や地元企業の会合、慶弔の会食などを取り込むべく、現在の本店所在地に自社物件を取得し、個室完備の高級和食店へと業態転換した。会席料理を基本に、旬の食材を使った「月替わり懐石コース」や、地元のブランド米と銘酒を組み合わせた「地産地消御膳」など、地域性を打ち出したメニューが特徴で、食材は県内の農家や漁業組合と直接契約して調達している。なかでも、地元産の和牛を使用した「特製すき焼き会席」は人気が高く、冬場の週末は予約が取りづらいことも多かった。
1990年代には、郊外のベッドタウンに二号店を開業。こちらは家族連れを主なターゲットとし、「釜めし御膳」や「お子様膳」などを提供するカジュアル和食業態として運営している。さらに2010年代初頭には、観光客の増加を受けて、駅前に小規模ながらもカウンター中心の割烹スタイル三号店を出店。調理場を囲む形式で、目の前で板前が調理を披露し、旬の一品を少量ずつ楽しめるスタイルが受け、インバウンド客からの評価も高かった。
しかし、少子高齢化と地元企業の接待文化の縮小により、2015年頃から売上は横ばいに転じ、特に平日の夜間利用が減少。さらにコロナ禍では予約のキャンセルが相次ぎ、宴会需要を柱としていた本店と郊外店は大きく落ち込んだ。一方で、カウンター割烹の三号店はコロナ収束後に若年層の支持を得て回復傾向にあり、SNS経由の予約が増加している。
このような変化を受けて、令和元年、都市部で飲食関連の企画・マーケティング会社に勤めていた現社長(創業家三代目)が事業を継承した。30代後半の現社長は、顧客層の変化やライフスタイルの多様化に対応する必要性を感じ、事業の構造転換を視野に改革を進めている。
まず取り組んだのが、ITツールの導入である。予約サイトやSNSを活用した広報戦略を整備し、InstagramやYouTubeで料理紹介や仕込み風景を発信することで、特に若年層への認知度が高まった。さらに、弁当や惣菜のテイクアウト商品を開発し、季節限定の「地元野菜のちらし寿司弁当」や「料亭の味・出汁巻玉子弁当」などが好評を得た。これらの商品は、近隣スーパーとの協業や道の駅での販売も試行されたが、店舗と並行して調理・配送を行う体制は確立されておらず、従業員の負担が増す結果となった。
一方、組織面では、現場の属人的な業務運営が課題として浮上している。特に本店の料理長を務めるK氏(60代後半)は、板前としての経験が長く、味の決定やメニュー構成を一手に担ってきた。後継となるべき若手職人は三名いるが、明確な技術承継の仕組みやマニュアルがなく、調理技術の伝承が不十分である。また、接客部門においても、20年以上勤務するベテランスタッフが中心で、新たに採用された若手との連携や教育に時間を要している。
人材確保の観点では、調理・接客ともに慢性的な人手不足に悩まされており、特に三号店では高いサービス水準を求められる一方で、固定スタッフが確保できず、都市部から移住してきた若手志望者をアルバイトとして雇用するなど、不安定な体制が続いている。待遇面でも、職能に応じた評価やキャリアパスが明確でなく、年功的な給与体系が継続していることから、若手の定着にはつながっていない。
その一方で、店舗間の協力体制も限定的であり、人員配置や仕込み業務の分担、ノウハウ共有などが属人的かつ非効率な状態にある。例えば、各店で提供する出汁や漬物などは共通であるにもかかわらず、仕込みは店舗ごとに個別対応しており、調理時間やコストに差異が生じている。現社長はこうした課題に対し、セントラルキッチン方式の導入や、デジタルによるレシピ管理、調理工程の一部標準化なども検討を始めているが、現場からは「伝統の味が失われる」との懸念も根強く、調整が進んでいない。
また、観光客や移住者といった新たな顧客層の獲得を見据え、メニューや店舗設計、広報戦略の見直しを模索している。外国人観光客の来店も増えていることから、多言語対応やWeb予約の整備にも着手した。こうした動きに呼応する形で、若年層や都市部からの移住希望者が料理人志望として門を叩く例も出てきており、社長は、従来とは異なる価値観や志向を持つ若手の採用と定着支援に可能性を感じている。
一方、長年の業務慣行や年功的な人事制度、明確なキャリア形成の仕組みがないことから、新たな人材の活用には制度面での見直しも必要と認識している。働き方の多様化に対応する柔軟な勤務体制や、技能と成果に応じた処遇制度への転換など、人事面の改革についても課題意識を持ち始めている。
A社は、創業以来受け継がれてきた地域密着の姿勢を大切にしながら、変化する外部環境に適応し、持続可能な事業運営の実現を目指している。現社長は、従来の成功体験にとらわれず、次世代の顧客・従業員にとって魅力ある企業となるべく、組織体制と事業の在り方を問い直し続けている。今後、A社が事業展開を行う上で、中小企業診断士に助言を求めている。(2208字)
設問
【設問1】
A社では、複数店舗の運営や新たな取り組みを進める中で、組織運営の面で問題が生じている。
A社の組織構造や役割分担に関する問題とその要因を100字以内で述べよ。
【設問2】
A社では、若手人材の採用・定着が進まず、熟練職人との関係構築も課題となっている。
A社の人材マネジメント上の問題点と、その背景にある人事制度の特徴を100字以内で述べよ。
【設問3】
A社は各店舗ごとに独立した仕込みや運営を行っており、業務の非効率性が課題となっている。
店舗間連携の課題と、その要因を100字以内で述べよ。
【設問4】
A社の現社長は、外部環境の変化に対応しながら、持続可能な経営体制の構築を目指している。
今後、A社が組織的に強化すべき施策を、人事面および組織面の両面から120字以内で助言せよ。
模範解答
【設問1】
各店舗が独立して運営されており、役割や責任分担が曖昧である。そのため、店舗間での仕込や仕入等に重複が発生し、非効率になっている。マネジメント層の配置や統括機能も不十分で、組織的な連携が図られていない。(100字)
【設問2】
年功的な処遇制度や不透明な評価基準により、若手の動機づけが困難。育成体系がOJTに依存しており、熟練者との関係構築や技能承継も進みにくい。人材定着に向けて職能評価とキャリアパスの提示が制度化されていない。(100字)
【設問3】
店舗毎に仕込や調理を個別に実施しているため、課題は共通メニューにおける工程の効率化で、原材料のロスや作業の非効率性を解消する。さらに、各店舗間での情報共有や業務標準化を図り組織的な業務連携に取り組む。
【設問4】
人事面は、評価制度の透明化とキャリアパスの整備により若手の定着と成長を促す。OFF-JTの導入や職種別研修を実施し、技能承継の仕組みを整える。組織面は、店舗間連携の強化と業務の共通化・標準化を進め、管理層を明確に配置することで、全体最適を図る。(117字)
解説
✅ 第1問 解説
設問の本質: 組織構造・役割分担に関する“現状の問題点”と“その背景”を問う問題。
🔍 出題意図
- 「理想=全社で役割分担され、統制のとれた運営」
- 「現実=属人的・分断的で重複や非効率が生じている」
🧩 与件根拠
- 「各店舗が独立」「店舗ごとに個別対応」「業務が重複」
- 「統括機能がない」「マネジメント層の不在」
📘 一次知識との接続
- 組織構造論:「機能別組織と事業部制」「統制の仕組み」
- 統合と分業:役割の明確化、責任の所在、ライン・スタッフ体制
🧠 解答の構造
- 現状:「店舗が独立」「分担曖昧」「非効率」
- 要因:「統括不在」「マネジメント欠如」
✅ 第2問 解説
設問の本質: 人材マネジメントの問題と制度的な背景(評価・育成・定着)
🔍 出題意図
- 「理想=若手がやりがいを持って定着し、技能を承継する」
- 「現実=モチベーションが低く、関係も築けず離職しがち」
🧩 与件根拠
- 「年功的処遇」「キャリア不明確」「OJT頼り」「関係構築が困難」
📘 一次知識との接続
- 人事制度設計:「等級・評価・報酬制度」「職能資格制度」「モチベーション理論(期待理論など)」
- 教育訓練:「OJTとOFF-JTの組み合わせが理想」
🧠 解答の構造
- 現状の問題点:「動機づけが困難」「承継が進まない」
- 背景・要因:「制度が年功的」「育成がOJT依存」
✅ 第3問 解説
設問の本質: 店舗間連携の欠如による業務の非効率という“構造的問題”を問う
🔍 出題意図
- 「理想=標準化・分担・共有による効率的運営」
- 「現実=重複作業・属人化・分断的運営」
🧩 与件根拠
- 「店舗ごとに重複」「標準化されていない」「情報共有不十分」
📘 一次知識との接続
- 業務プロセス設計:「標準化・マニュアル化・ベストプラクティスの共有」
- 組織間連携:「共通業務の集中化」「バックヤードの共通化」
🧠 解答の構造
- 問題点:「重複・非効率」「連携不全」
- 要因:「標準化なし」「情報共有なし」
✅ 第4問 解説(助言問題)
設問の本質: 現状の問題を踏まえた「今後の施策」を、人事+組織の両面から助言させる設問
🔍 出題意図
- 「今後どうするべきか」を構造的・制度的に述べさせる
- 抽象的でなく、施策レベルで具体的に
🧩 与件の裏テーマ
- 「評価制度の再設計」「キャリアの可視化」
- 「技能承継と教育制度」「業務の標準化」「マネジメント配置」
📘 一次知識との接続
- ✅【人事施策】「サ・チ・ノ・ヒ」=採用・賃金・能力開発・評価
- ✅【組織施策】「ケ・ブ・カイ・ネ・コ」=権限・部門・階層・ネットワーク・コミュニケーション
🧠 解答の構造
- 人事面の施策:「職能評価」「キャリア提示」「育成制度」
- 組織面の施策:「業務共通化」「情報共有」「管理体制構築」