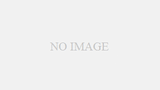こんにちは、からすこです。
早速トレーニングです。
与件文
A社は、東北地方の沿岸地域に本社と工場を構える水産加工業者である。創業は昭和30年代、初代社長が家族と共に地元港で水揚げされたイカやサンマを加工し、塩辛や干物として周辺の商店や旅館に卸すところから事業を始めた。当時は冷蔵設備も乏しく、手作業での塩漬けや天日干しによる保存が主であったが、素材の鮮度と丁寧な仕事ぶりが評判を呼び、地元での取引先を少しずつ増やしていった。
二代目社長の代では、漁協との関係を強化し、イカやホヤ、メカジキといった沿岸地域特有の水産資源を安定的に仕入れる体制を整えた。また、冷凍技術と真空包装機の導入により、商品の保存性が向上し、県外の百貨店や生協といった販路への出荷が可能となった。この時期には本社工場の増設とともに、衛生管理体制の見直しを図り、HACCPに準拠した製造環境の整備が進められた。これにより、業務用の業者からも高い信頼を得て、取引が拡大した。
製造部門の中核を担っていたのは地元出身の中途採用社員や、長年勤める熟練パートであり、彼らの技能に支えられて安定的な生産が続いていた。一方で、人材育成は現場任せで体系化されておらず、新人がベテランに倣って作業を覚える形が続いていた。
三代目で現社長は、創業者の孫にあたる。大学では経営学を学び、卒業後は大手食品メーカーにて商品企画や販促の実務経験を積んだ後、10年前にUターンしA社に入社した。当初は新設された商品開発部門を率い、地元食材にこだわった新しい加工品の開発を行った。特に、観光客向けにホヤの燻製やメカジキのしぐれ煮など、土産物に適した商品を道の駅や物産館で販売し、ブランド認知の向上に貢献した。
しかし近年、A社を取り巻く経営環境は厳しさを増している。まず、地域の水産資源が年々減少し、イカやサンマといった主力原材料の確保が難しくなってきている。漁期の短縮や天候不順など、気候変動の影響も無視できず、仕入価格が高騰する中で利益確保が難しい状況となっている。
さらに、地域全体で若年層の流出が続いており、製造部門ではパート・アルバイトの平均年齢が60歳を超えている。繁忙期の安定稼働を支えていた熟練作業員が体力面の限界を感じるようになっており、今後の人材確保と技能承継が喫緊の課題となっている。現在、社員構成は正社員15名、パート・アルバイト25名だが、新卒採用の実績は少なく、若手社員の定着率も高いとは言えない。
現社長は、こうした状況に危機感を抱き、業容の再構築を目指している。具体的には、従来の業務用卸に依存する構造から脱却し、EC販売やインバウンド対応を含めた個人向け商品展開を強化している。コロナ禍以降、家庭内消費やお取り寄せニーズが拡大したことを受けて、自社ECサイトのリニューアルや、楽天市場・Amazon等への出店を進めた。
また、外国人観光客の土産需要を見据え、英語・中国語によるパッケージ表記や、アレルゲン表示・ハラール認証に対応した商品も検討している。現在は試験販売の段階であるが、SNSを活用した情報発信やレビュー分析を行うなど、販売戦略にも工夫を凝らしつつある。
とはいえ、これらの新たな取り組みを支える社内体制はまだ整っていない。社内にはITやデジタルマーケティングの知見を持つ人材がおらず、販売実績の集計や分析は、Excelベースで一部の社員が属人的に対応している。また、商品開発と製造、営業がそれぞれ異なる部門で運営されており、商品コンセプトの社内共有が不十分なまま製造に入ることもある。その結果、販促タイミングと在庫がかみ合わず、販売機会を逸するケースも見られる。
現社長は、こうした機能間の断絶を解消し、スピード感を持って施策を展開できる柔軟な組織体制を構築したいと考えている。その一環として、部門横断のミーティングや情報共有ツールの導入を進めているが、現場では「実務が優先」「慣れたやり方が安心」という空気が根強く、変革への抵抗感も残っている。
人事制度にも構造的課題がある。A社では長らく、勤続年数と年齢を重視する評価制度が運用されており、能力や成果への評価が曖昧である。そのため、商品開発や営業といった挑戦を要する業務においても、若手社員の提案が十分に反映されず、意欲の低下や早期離職に繋がっている。社員間にも「どうせ評価されない」という諦めがあり、組織の活性化が進みにくい。
このような課題を踏まえ、現社長は今後の経営改革に向け、①商品開発から販売までの部門連携強化、②人事制度の見直しによる人材定着・活性化、③ECや海外展開を支える人材基盤の構築、の3点を中核課題と位置づけている。2025年度からは外部の中小企業診断士と連携し、経営改善計画を策定。国の補助制度を活用して、社内システムの見直しや設備更新、テストマーケティングによる販路開拓を進めている。
今後A社には、地域資源を活かしながらも、より広域かつ持続可能な経営モデルの構築が求められている。(2005字)
設問
【設問1】
A社の現在の経営における強みと弱みを、それぞれ40字以内で簡潔に述べよ。
【設問2】
A社の部門間連携に関する組織的課題について、与件文の内容を踏まえて100字以内で分析せよ。
【設問3】
A社の人事制度上の問題点と、それが若手人材の定着・活性化に与えている影響を100字以内で述べよ。
【設問4】
A社が今後、販路拡大や経営改革を進めるにあたって、人事・組織面で留意すべき点を100字以内で助言せよ。
模範解答
【設問1】
強みは地域水産資源と加工技術を活かした商品開発力、観光販路への展開力、HACCP対応の衛生体制。弱みは年功的評価制度、人材育成不足、部門間連携の欠如と情報共有の遅れ。
【設問2】
商品企画、製造、営業の各部門が縦割りで運営され、商品情報や需要見通しの共有が不足している。部門間で販促と在庫を調整し、施策を円滑に実行するための情報連携体制の確立が、組織的課題である。
【設問3】
年功的な評価制度により、能力や成果が正当に処遇に反映されず、若手社員の提案が埋もれている。挑戦が報われない組織風土は意欲を低下させ、定着率の悪化や活性化の停滞といった悪循環を生んでいる。
【設問4】
販路拡大に対応するため、IT・マーケティング分野に強い人材の外部採用と社内育成を推進すべき。さらに、部門間の連携を強化するプロジェクト型組織を構築し、全社的な戦略の共有と実行体制を整える必要がある。
解説
✅ 解説構成
- 出題意図:設問が何を問うているか(診断士としての視点)
- 与件対応:与件文のどこにヒントや根拠があるか
- 一次知識適用:解答に活かすべき知識体系や理論
- 解答構造:模範解答がどのように構成されているか
■ 設問1 解説
A社の現在の経営における強みと弱みを、それぞれ40字以内で簡潔に述べよ。
1. 出題意図
- 企業内部の資源や体制を分析し、要点を短く整理できる力を問う。
- SWOTの「S(強み)」と「W(弱み)」を具体的に見つけ出せるかが問われている。
- 抽象語ではなく、他社との差別化要素や改善対象となる構造的課題を短く的確に言語化する能力が評価される。
2. 与件対応
- 強み:地域の水産資源、加工技術、HACCP対応の衛生体制、観光販路、商品開発力。
- 弱み:年功序列的評価制度、育成体制の未整備、部門間の情報共有の遅れ。
3. 一次知識適用
- 強みは「経営資源論」や「差別化集中戦略」。
- 弱みは「人事制度設計論」「組織構造論(職能別組織の弊害)」。
4. 解答構造
- 「強み:素材+技術+展開力」「弱み:制度+育成+連携不全」という3要素対3要素で対称構成。
- 単語数制限の中で網羅性と読みやすさを意識。
■ 設問2 解説
A社の部門間連携に関する組織的課題について、与件文の内容を踏まえて分析せよ。
1. 出題意図
- 組織の機能的な構造や情報連携の状態を評価し、**現状のギャップを埋める取り組み(=課題)**として整理する力が問われている。
- 「課題」は単なる問題指摘ではなく、理想と現状の間を埋めるアクション。
2. 与件対応
- 商品企画、製造、営業が縦割り。
- 情報共有不足により販促と在庫のタイミングが合わず、販売機会を逸する。
- 属人的な運営に頼り、全社的な連携が機能していない。
3. 一次知識適用
- 職能別組織構造の特徴と限界(部門間断絶、セクショナリズム)。
- 情報共有とクロスファンクショナルチームの重要性。
4. 解答構造
- 「現状の構造と課題」→「取り組むべき方向性」→「その意味付け(課題としての意義)」で論理的に展開。
■ 設問3 解説
A社の人事制度上の問題点と、それが若手人材の定着・活性化に与えている影響について述べよ。
1. 出題意図
- 人事制度が社員の行動や感情(モチベーション)にどのような影響を与えるかを因果関係で説明できるか。
- 特に若手社員の意欲・定着率・組織活性化との関係に着目。
2. 与件対応
- 年功的な評価制度が継続。
- 成果や提案が反映されず、若手が評価されない。
- 意欲低下、早期離職、組織が停滞。
3. 一次知識適用
- ハーズバーグの動機づけ理論:成果の承認や成長機会の欠如は不満要因。
- 人事評価制度:成果主義・能力主義との比較。
4. 解答構造
- 「制度の不備」→「若手への影響(提案埋没、意欲低下)」→「定着率悪化・活性化停滞」という三段構成で展開。
■ 設問4 解説
A社が今後、販路拡大や経営改革を進めるにあたって、人事・組織面で留意すべき点を助言せよ。
1. 出題意図
- 将来の戦略展開に向けて、人材・組織体制の両面から実行可能な助言ができるかを評価。
- 「戦略は組織に従う(チャンドラー)」の原則に基づき、組織設計と人事施策の整合性が問われる。
2. 与件対応
- ECやインバウンド展開を見据えた改革意図。
- IT・マーケティングに関する知見の不足、属人的業務の課題。
- 部門間の縦割り構造、情報共有の遅れ。
3. 一次知識適用
- 人事:採用・育成・タレントマネジメント。
- 組織:プロジェクト型組織/機能横断体制/戦略共有の必要性。
4. 解答構造
- 人事面の留意点(スキル確保)→ 組織面の留意点(連携・推進体制)→ 戦略との結びつき、という三段構成。